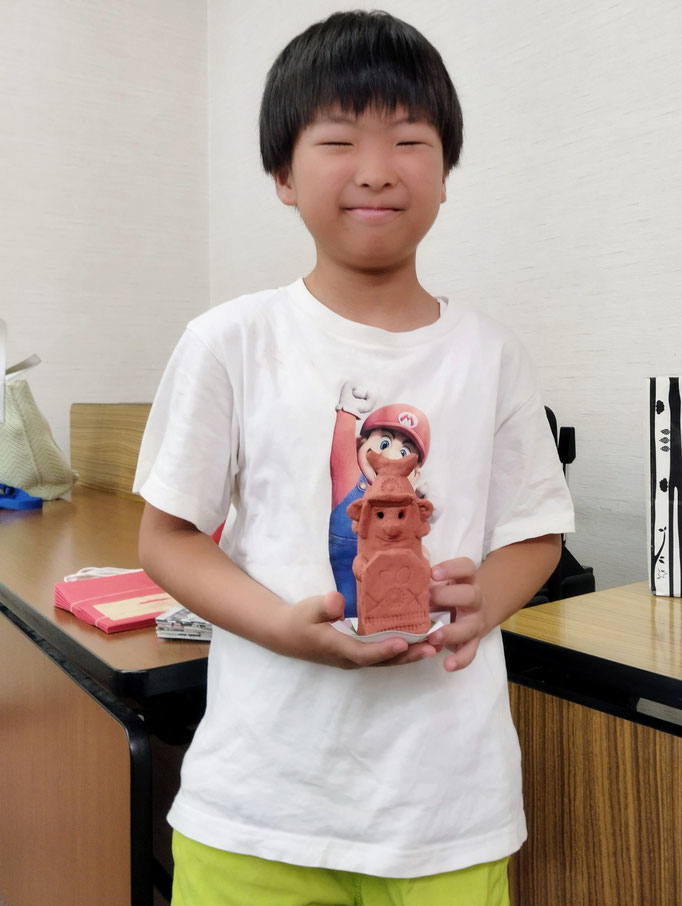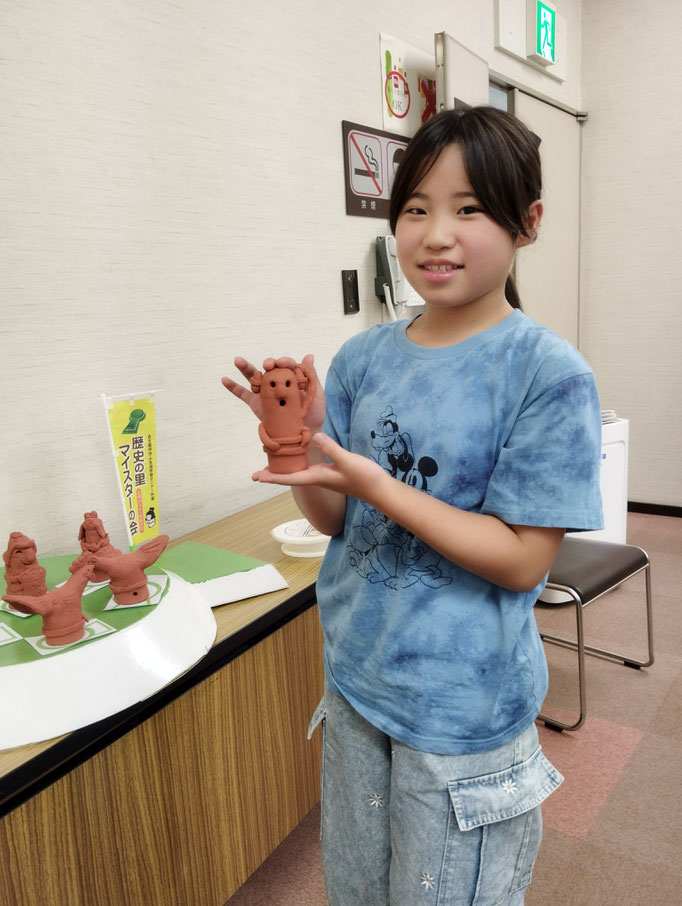あつい、あつい、夏休みも残りわずかとなりました。「夏休み宿題応援」と題して(とは言っても大人も参加できます)ミニサイズの埴輪づくりに16名が体験されました。

繊維入りの焼かない粘土を使います。粘土を板状に延ばして芯に巻き、中空の埴輪を作ります。
粘土の両脇に木の板を置いてローラーで延ばせば、厚みが均一な粘土板ができます。これを型に合わせて切り取ります。この工程を、馬ひき埴輪は1回、盾持ち人埴輪は盾を含めて2回、鶏埴輪は尾羽根を含めて3回、しだみこちゃんは髪とスカートを含めて4回行います。
これでおおまかな形が出来上がりましたので、あとは自由に創作してもらいます。
夏の埴輪づくりは乾燥との闘いです。手のひらが粘土の水分を吸い取ってしまい、細かいパーツはすぐに硬くなってしまいます。
アンケートには、
「くっつけるのにすぐかわいて、かたぬきは力をつかうから」むずかしかった(小2)と書いてくれました。繊維が入っているせいで、切りにくのが難点です。
「粘土になれていなくて、形をとるのがむずかしくかった」(大人)
「くっつけるときに、つまようじできれいにできた」(小4)
「顔、体、たてをかんたんに作ったから」とても満足(小2)。
大人よりも簡単に感じた子どもがいたようです。
「ねんどのつかいかたがわかったから」とても満足(小3)。
「かおのばらんすがちょっとうまくいかなかったけど、つるつるにできたし、おもしろかった」(小4)。
少し乾いてきた頃にストローで撫でると、粘土に入っている砂が中に入り込んで、表面がつるつるになります。古代の人たちも、土偶や土器を作るときは磨いて表面をつるつるにしています。
馬ひき埴輪を作った女の子は「せっけいずをいえでかいたから」とてもうまくつくれた(小2)と書いてくれました。。設計図を見たかったですね。
笑う盾持ち人埴輪やヒヨコを背にのせた鶏埴輪など、アレンジを楽しんでくれたようです。
最後に、快く撮影に応じてくださいました皆さま、素敵な笑顔をありがとうございます。